2025年9月27日に配信されたYouTubeチャンネル「masayaのおしゃべり喫茶」の「【第15回】初ゲスト!膠原病の認知度を考える【みんなのおしゃべり広場】」では、MCのmasaya、naoと共に、株式会社ピアハーモニーの深井さんと木下さんをゲストに迎え、膠原病の認知度調査の結果について深く掘り下げて議論しました。
ピアハーモニーは、難病患者さんやご家族の抱える現状がまだ社会に十分に届いていないと考え、「患者さん自身の声を医療現場や製薬会社の皆様に届けること」をミッションに活動されている企業です。

今回は、共同で実施した膠原病の認知度調査の結果をもとに、認知度の現状と課題について語り合いました。
※ 出演者の会話は要点をまとめています
調査結果1:膠原病という言葉を知っていますか?
無作為に選ばれた300名に対して実施された調査の結果では、膠原病に対する認知度の低さが明確になりました。
• 初めて聞いた:49.3%(約半数)
• 名前だけ聞いたことがある:30%
• 説明ができる:3.7%
この結果に対して、参加者で次のような意見交換をしました。
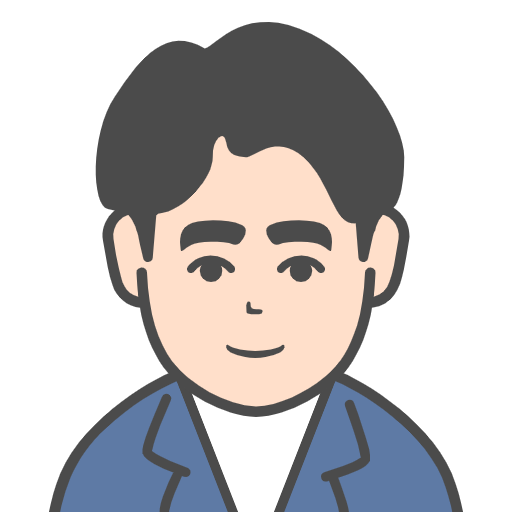
私は、妻が膠原病に罹患する前は「名前だけ聞いたことがある」という立場だったので、この結果は妥当だと感じています。

正直なところ…調査前は『もっと認知度が高いのでは?』と思っていました。仕事柄、私の周りには患者さんが多いので、約8割が「初めて聞いた」「名前だけ知っている」という結果には驚いています。
裏を返せば、膠原病であるということを当事者やご家族が周りの方々に伝えることができていない現実があるのではないでしょうか。

この病気に罹患している人は、話をする相手が病気に関する知識を全く持たない前提で、自分の症状や状況を周囲に伝えることになるわけですね。

膠原病は、風邪や骨折などと違い、パッと(短い時間で)説明できる病気ではないですよね。様々ある疾患の総称であることが、説明を難しくしているところがあるようです。
病名自体の表記の難しさが理解を妨げる要因として挙げられました。「膠原病という言葉の由来がコラーゲンであったり…今一つピンとこない」など、病名と語源が症状に結び付きづらいことも、認知度が高まらない要因かもしれません。
調査結果2:膠原病に対してどのようなイメージを持っていますか?
膠原病に対するイメージについての質問では、「イメージがない」という回答が圧倒的多数を占めました。

「治らない病気」(17%)と答えた人が少ないことから想像すると、「難病である」や「生活に支障が出る病気」だと回答している人も実際には具体的なイメージができておらず、「簡単な病気なのかな?」と思っている可能性はありますよね。

「治らない病気」と答えている人は、大雑把でありながらも外観を正確に捉えていると感じます。この回答が一定数あったことを嬉しく思います。
周りから「病気が良くなったら(治ったら)また遊びましょう」といった言葉が良く出るので、このような理解が広がってくれると、患者さんの落胆も減るのではないでしょうか。

「病気は治療して完治させるものだ」という一般的な認識と、膠原病は「日々何かしらの治療を続けながら、生活しなければならない」という現実との間に、大きな理解の差があると感じます。

一方で「治らない病気」と回答した人の数(51人)に対して、「就労や日常生活が制限される」という回答(39人)が、少ないとも感じます。
病気になった結果、生活、仕事、ライフスタイルが脅かされるのだという現実が、理解されていないのだと思います。
認知度の低さが生む摩擦とは?
患者の悩みの一つとして、免疫力の低下からくる感染症への警戒(人混みの忌避)があります。このような見た目からは想像しにくい苦労は、周囲にはなかなか理解してもらえないものだと考えられます。
見た目に変化がないと、患者の苦労も周りからは見えにくいということではないでしょうか。
そして、イメージがない現状が「患者と周囲との溝を作っている」とも考えられます。それは周りの人が悪いのではなく、「病気のことを分からない」からこそ、どう接したらいいか分からない状況が生じているのだと考えられます。
YouTubeのコメント欄(Keicoさんより)
ステロイドの副作用で太ると、周囲から「元気になったね」と言われ、「そうじゃないんだけどなぁとモヤモヤします」という複雑な気持ちを共有いただきました。
調査結果3:どのような検査によって診断が確定するのか?
ほとんどの人が「どのような検査なのかがわからない」という回答結果になりました。
膠原病の診断は、血液検査一つで単純に決まるものではなく、血液検査、組織の検査、画像検査など、様々な結果を専門医が複合的に判断して、ようやく確定診断に至ります。
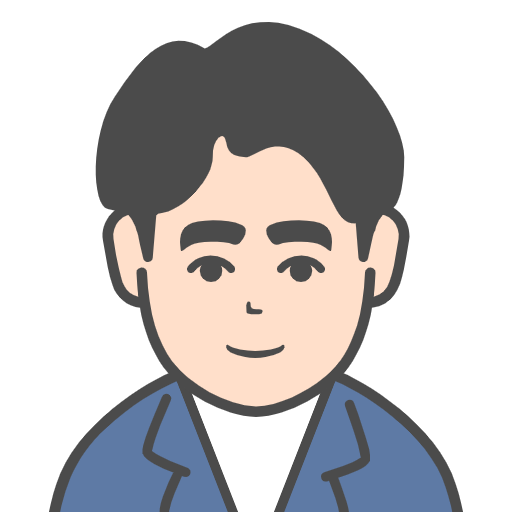
「血液検査」という項目が思ったよりも多かったので、イメージがない中でも、おおよそ正しい認識をされているのだと感じました。

膠原病に限らず、血液検査がどの疾患でも検査の基本になっています。
一部の難病は確定診断を得るために遺伝子検査が必要というケースもあるようです。膠原病が遺伝子検査では確定診断に至らないところから考えると、膠原病が遺伝子系の疾患ではないことを示していると言えますね。

血液検査に加えて、呼吸器系の疾患では「呼吸器検査」なども一般的には加わります。疾患によって様々ですが、この選択肢であれば血液検査という回答が多いのも頷ける結果です。
患者さんの中には、本人ですらどの検査が決め手で診断されたのか分かっていないケースも多いようです。

確かに…そうです。患者さんにインタビューをすると「入院している最中に診断されました」とおっしゃるだけで、何が決定的な診断だったのかが分からない方もいます。その確定診断の決定プロセスは患者にとって不透明なことが多いようですね。
初期診断から診断確定までのプロセスが明確になることで、体調が悪いときに「こんな検査を受けてみたいな」といった行動喚起につながると思います。
その意味で、症状が出てから診断されるまでの経緯をもっと明確にできるように伝えていかなければなりません。
患者側も、症状を訴えるだけで膠原病の検査に行きつくことを期待するのではなく、自ら能動的に検査項目にかかわっていく必要があるのかもしれません。
調査結果4:体調不良で膠原病の疑いがあると感じたらどうしますか?
体調不良時にどのような行動をとるかという質問では、以下のような結果が得られました。
• 何もしない:34.7%
• ネットで情報調べる:26.3%
• すぐに専門医を探す:23.3%

イメージがないと「行動を起こすことすらできない」ということだと思います。
家族や自分自身に症状が出ても、イメージがないわけですから「そのうち良くなるだろうな」「放っておけばいいかな」と判断してしまうのは、仕方がないことかもしれませんね。
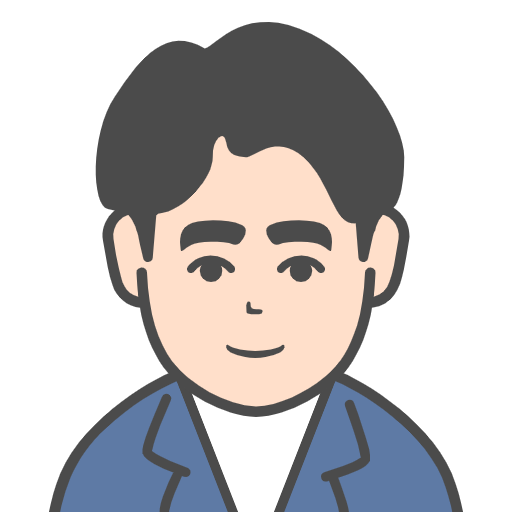
妻の初期症状(関節の痛み)が出た際、ネットで調べても膠原病にはたどり着きませんでした。リウマチや更年期障害の可能性は考えていましたが、整形外科に行っても、専門医に診せても、「血管炎」までの確定には至りませんでした。

専門医を探すのはなかなか難しいですよね。関節が痛ければ、整形外科に行くことが一般的ですから。
初期症状だけだと、医師も他の病気と思ってしまうケースが多いようです。様々な初期症状がある中で、自ら「膠原病かな?」と思い浮かべる人も少ないと思われます。
抜本的な解決策はないものの、患者側から「先生!ひょっとしたら膠原病の疑いはありますか?」という一言を言える環境ができることが重要かもしれません。
まとめ:啓発活動の重要性
今回のアンケート結果から、「イメージがない人の数=動けない人の数」という結果になっていると推察されます。
初期症状が出た際「膠原病かもしれないな」「先生に少し相談してみようかな」という人の数が増えていくことが望ましいでしょう。そのためにはやはり、認知度を上げることが必要になってきます。
関節リウマチやSLEを含めれば「実は相当数の患者さんが同じ職場にいるはず」です。膠原病の患者さんは少なくないわけですから、社会全体で意識が高まる可能性は十分にあると感じられます。
今回の調査を通じて、膠原病の認知度と、それによってもたらされる理解のギャップが浮き彫りになりました。
膠原病PR協会ミライでは、今後も患者さんの状況を通じて、周囲に膠原病の認知度を高める活動を行い、多くの人が早期発見につながる活動を続けてまいります。
